【第3章】「成熟」へのステージ
いま”を更新し続ける 平成12(2000)年〜平成27(2015)年/72歳〜86歳
日本シニア・ゴルファース協会守護
地位確認訴訟に勝利
旅から戻れば、また“世俗”の日常に立ち返らなければならない。70歳を超えたころから、さまざまな旅と日常の往復運動が増えてきた。旅には海外に及ぶものもあり、友人・知人を訪ねる小旅行もある。
しかしここでは、先に“世俗”の話をしておこう。愉快で実のある話はあとからゆっくり楽しむ方がいい。この“世俗”の話は二つあるが、どちらもゴルフに関係する。
まず一つ目の話は、日本シニア・ゴルファース協会(以下JSGAまたは協会とする)に係る出来事である。
私は、平成4(1992)年以来、JSGAの組織運営を担当する総務委員を拝命していたが、その運営の仕方に関連して理事の間にコミュニケーションの齟齬が生じていたため、しばらく距離を置いていた時期があった。
ところが、平成12(2000)年頃、大変な事件が起こった。このJSGAの乗っ取りを謀ろうとする人物(仮にM氏としよう)が現れたのである。
本来、JSGAの専務理事は原則として無給の役職だが、このM氏は有給の専務理事になろうと画策し、さらには当時の主要メンバーの一人、W常務理事(総務委員長)を追い落とそうとした。
これに気付いたW常務理事(総務委員長)がM氏の身元を調べたところ、何とこの男は警視庁の総会屋リストに載るような人物であることが判明したのだ。するとW氏はこれに嫌気がさして身を引いてしまった。勢いに乗じたM氏は老齢のY会長を籠絡し、新たにA氏を会長に据え、自分が専務理事になる役員人事案を会員総会に上程したのである。W氏は身を引いたが、JSGAの歴史と伝統を守ろうという会員も多く、当然のことながら総会は大もめになり,収拾がつかない状態で幕になった。
問題はこれだけで終わらなかった。当時のJSGAには4,000万円の銀行預金残高があったのだが、この総会直後、M氏は銀行窓口で「昨日の総会でA氏が会長に選出された」という書類を見せて預金を引き出そうとしたのだ。
銀行というところは、当然のことながら、トラブルの“匂い”のする引き出し要請には慎重である。M氏の要請には簡単には応えなかった。
M氏の引き出し要請を訝った銀行は、日頃取引きをしているJSGAの事務窓口に連絡を入れてきた。驚いたのは協会事務員である。その事務員は、逆に届け出済のY会長印鑑を持って引き出そうとした。しかし、これも断られてしまったのだ。なぜか?
当時のJSGAは任意団体(法律上は「人格なき社団」と言う)であるから、社団法人や株式会社のように代表者名が登記されていないので、4,000万円の預金も法律上は個人預金と同列で、もともとは会長であるY氏の形式的な名義で預金されていたのだ。
ところが、銀行側にしてみれば、突然、A氏とY氏の2人の名義人が現れたことになる。そこで銀行は、誰が正当な会長であるか裁判で決着をつけてから申し出ないと預金は渡せないと主張してきた。これは、一般論から言えば、銀行の立場としてはやむを得ない判断だった。もし、拙速に判断してどちらかの名義人に預金の引き出しを許してしまえば、もう一方の預金名義人から責任を問われかねないからである。
そうなると、Y氏が正当な会長であることを認めてもらうには、地位確認訴訟という裁判で決着をつけなければならない。面倒なことになったものだ。
しかも、このとき乗っ取り犯のM氏らはJSGAの会員に怪文書を送りつけ、A氏が先の総会で会長に選任されたと盛んにPRした。しかし、それでは協会はダメになると考えた有志は結束してA氏に対抗することになった。その中心は公認会計士のK氏と某ゴルフ場オーナーのF氏である。
事態がここまでに至ったある日、そのF氏から私に対して大変に熱のこもった協力要請が寄せられた。Fさんとはかつて日米親善ゴルフ競技大会でアリゾナへ10日間ご一緒した仲だ。そのFさんが有無を言わせぬ語調で「こうなった以上は、まさに君の出番だ!」と言ってきたのだ。そして、あまりに熱心なFさんの語り口に、私の正義感に火がつけられてしまったのである。
この訴訟に当たって協会としては会員のT弁護士に弁護を依頼することになった。そのT氏によれば、当方(Y氏)が正統な協会会長であるということを証明するには、過去の理事会議事録等詳細な書類を提出する必要があると言う。Fさんが言っていた私の「出番」とは、まさにこの仕事を担うということにほかならなかった。そこで私は総務委員長の肩書きを頂戴することになったのである。
JSGAは日本ゴルフ協会(JGA)からシニア部門が独立したという歴史的な経緯があった。そのため、発足当初からJGAに倣ってきちんとした協会運営がなされており、幸いにも議事録等資料もよく整理・保存がなされていた。
その整った議事録等の資料を検討した裁判官は、当方のY氏が本物の会長であることはわかっていたようだが、決着は判決ではなく示談で解決するよう強くアドバイスを受けた。一般に「人格なき社団」の地位確認訴訟は示談による解決が通例だというので、私たちはこのアドバイスを受け入れることにしたのだ。それまでずいぶんとご苦労をおかけしてきたT弁護士も、示談による早期決着の腹を決めておられたと思われる。
そして、最終の示談のため裁判所に赴いたとき、裁判官は協会代表としての私に対してこう提案してきたのだ。
「あなたの方が正当な会長であることはわかっていますが、先方も事務所まで作ってやっているわけですから、600万円払ってあげてはいかがですか?」
もちろん、これは受け入れられるものではない。私は強く反論した。
「乗っ取り犯に追銭までやるのですか?」
その後、何回か原告・被告双方が入れ替わり立ち替わり裁判官と話し合った結果、示談金400万円で妥結したのである。
なおこのとき、「今後、相手の批判・非難は避けるように」と言うクローズが補則されたので、これ以上の内幕は割愛するが、JSGAにとって、さらなる時間と労力を費やして訴訟を継続するよりも、この400万円程度の金額で得た経験知の方がずっと価値があると考えている。
ここで得られた重要な経験知とは、任意団体(人格なき社団)というのは法律的にはトラブルになりやすい不安定要素を持っており、したがって、予め法人格(例えば一般社団法人など)を持たせて法律的にその団体を保護することが肝要だということである(この経験知は、その後、後述する別の団体にも活かされることになる)。
この1年半に及ぶ地位確認訴訟の示談以後、私はJSGAの専務理事と副会長を引き受け、平成17(2005)年には一旦この職を辞したが、平成20(2008)年には再び専務理事を拝命した。
この専務理事の時代、それまで許認可手続きのむずかしかった公益法人の法律が改正されたこともあって、JSGAとして過去の災いを再び繰り返さないため、平成23(2011)年に定款等も作り直し、JSGAは一般社団法人として登記を果たした。
ちなみに、平成25(2013)年6月にはこの専務理事も退任し、現在は顧問という立場にある。

東松山CC、2期目の社長に
食堂経営の健全化に着手
ゴルフにまつわる二つ目の話は、当時、理事長を務めていた東松山カントリークラブ(以下東松山CC)の経営にその後も係わり続けたことだ。
平成13(2001)年6月、理事長職を継続していたが、運営会社側にはまだ経営上の課題が残されていたので、再び社長の職に就くことが理事会で承認された。つまり、理事長と社長の兼務である。前回の社長時代に借金は全て返済したとは言え、まだ健全経営とは言いがたい状態の会社をそのまま見捨てるわけにはいかなかったのだ。
その課題の一つは、ゴルフ場の食堂経営の健全化だった。
「東松山CCの食堂は安くてうまい」という評判だったが、財政的には厳しい状態にあり、これを立て直すには会社組織としての経営努力を必要としていた。ところがその最中、前年(平成12年)1月に、食堂部の責任者である部長が突然、辞めると言い出した。もちろん留意したが本人の意志は固く、3月には退職してしまったのだ。ここにきて食堂部門の立て直しは、従業員の給与体系を柱とする財政と組織の両面から考え直さなければならない事態になったのである。
私が2度目の社長を引き受けたのは、この重要課題を何とかしなければならないとの思いがあったからだ。

当時の食堂の運営は、食材の仕入れから料理、配膳に至るまで、すべて自前で行われていた。しかし、年功序列の給与体系を採用している限り、トータルな人件費が不安定な財政を圧迫する要因の一つになっていた。特に食堂部門には勤続年数の長い従業員が増えていたせいもあって、他部門に比べて厳しさが集中していたのである。
この事態を知った理事の一人が、食堂部門の事業全体を外注に出すべきだと言い出した。計算によると、外注することによって年間7,000万円ほど浮くというのである。しかし、そのためには20人以上の従業員を解雇しなければならない。
前回の社長就任から理事長を経て、すでに6年間も従業員たちと親しくしてきた私である。会社経営を一緒に支えてもらうために、一緒に社員旅行に出かけたり飲み会などを催したりして、胸襟を開いてきた従業員たちのクビをそう簡単に切ることはできない。
もちろん、経営を与っている以上、当時の財政事情の厳しさは百も承知だ、しかし、従業員のリストラではなく、作業効率化や経費削減の努力などによる営業収支の改善という方向を模索したいと考えた。
しかし、実際に食堂部門の営業収支だけで財政の全体までを改善できるかどうか、理事会を納得させなければならない。そこには信頼に足りる客観的な根拠が必要だった。そのため、2度目の社長を引き受ける前年(つまり理事長のとき)から、ゴルフ場経営専門のコンサルタント会社に診断を依頼していたのだ。
そして1年後、社長に再任された私のところに、そのコンサルタント会社による報告が上がってきた。
ところが、残念な結果が出てきてしまったのだ。調査を担当してくれたコンサルタントのFさんによるとこうである。
食堂従業員の一人ひとりと面談して聞き取りをしたが、彼らのモラール(やる気)にバラツキがあり、また食堂部門のリーダーシップが機能していないため、全体的としては士気の低い方へと引きずられる傾向は否めない。
「伊室さん、これでは営業収支の改善は望めません。外注するほかありませんよ」
コンサルタントの提言は最大限に尊重するというのが、診断を依頼するときの理事会との申し合わせだった。そこに動かしがたい客観的な診断が出てしまったのだ。仕方がない。私は腹を決めなければならなかった。
食堂部門の外注ということに決まれば、従業員の解雇を通告するのは社長である私の仕事だ。食堂の従業員全員にしっかりと説明しなければならない。従業員たちに集まってもらい、私は説明を始めた。
「現状のままでは会社が立ちいかないのです。本当に申し訳ないことですが、雇用契約を解約させてください」
この言葉の前後にもう少し挨拶めいたことは言ったと思うが、基本的な骨子はこれだけである。私からの説明は5分ほどであっけなく終わってしまったのだが、直後に1〜2分の沈黙があり、その間、従業たちはうつむいているばかりだ。私も黙って彼らの顔を見ているしかなかった。
と、そのとき、日頃はおとなしいベテラン女性従業員のIさんが声を上げた。
「伊室さん、あなたは前に『外注には反対だ』と言ってたじゃありませんか。これから私たちの生活はどうなるんですか。路頭に迷わせるつもりですか!」
この一声がきっかけとなり、紛糾したその場は、約3時間にわたって私の糾弾集会と化してしまったのだ。普段にこやかに私と会話を交わしていた彼らが、一斉に私を攻撃し始める。なかには涙を流しながら訴える女性従業員もいた。
「残業代ももらわずに、休暇も取らずに、がんばってきたのに、突然クビとは、何ごとですか!」
もちろん、彼らの気持ちは痛いほどわかる。当然の言い分だ。逆の立場なら私も同じことを言うだろう。私は、従業員たちの罵声混じりの批判を一身に受けるしかなかった。ただ、それでも彼らに少しでも納得してもらえる手立てを考えていたことも確かだ。
その場はなかなか収まらなかったが、私の方から、解雇に当たっての条件を近々に知らせるということを告知して、何とか解散してもらうことにした。
そして後日、解雇の代替条件として出したのは、次のようなものだった。
一、過去に支払われていない残業代は全額支給する。
一、消化されていない有給休暇については、当面、同じ日数だけ代替の休日とする。
あるいは、その日数分の給与を日割り計算で支給する。(その両方も可)
結局、食堂部門の外注先はあるデパートの食堂運営をやっている会社に決まった。その会社は、いままでのゴルフ場食堂の従業員から、ほんの数人だが、再雇用してくれた。そのうちの一人は、私が解雇を通告した際に、私を最も勢いよく糾弾した女性従業員の一人、Sさんだった(彼女もベテランである)。
彼女は現在も東松山CCの食堂に勤務しているが、かつて私に挨拶してくれたときの笑顔は、このとき以来見せてくれたことがない(笑)。それでも私は、いまも彼女へのにこやかな挨拶を欠かしたことはない。
もう一つの重要課題、地代軽減化
本物のゴルフ、本物のゴルフ場へ
東松山CCの二度目の社長就任時には、もう一つ重要な課題解決の仕事が待ち受けていた。地主に支払う地代軽減化という課題である。
一般にゴルフ場は、土地を購入してゴルフ場コースを造成しているが、東松山CCでは9ホールを増設するとき54人の地主から土地を借りたのである。
バブル最盛期に借りたわけであるから地代も望外の高さで、おまけに消費者物価指数の変動に応じて変わるという条件までついていた。
最初の契約時(昭和60年)の地代は、当初1㎡当たり200円だったのだが、平成10(1998)年を過ぎた頃から1㎡当たり240円代にまで上がっていたのだ。この額は、当時の一般的な相場から言っても相当に高い水準のものであり、しかもバブルが弾けてもそんな地代を払い続けていたのでは、このゴルフ場は保たないというのはわかっていた。しかし土地貸借契約の満了までは、これを守らなければならなかった。
しかし、高額な地代を払い続けていく限り、経営を健全化することができないので、思い切って地主会長に地代の値下げ要請をぶつけたのである。もちろん最初の反応は芳しくなかったが、それでも私は何とか会長を納得させるべく、いろいろ説明を試みたのだ。
「会長さん、このままではこのゴルフ場は潰れてしまいます。もしそうなったら、外国のゴルフ場会社が乗り込んできて、実に厳しい契約内容を迫ってきますよ。地代なんて二束三文も同然。おそらく1㎡当たり50円も出さないでしょう」
私はこう言って、地代を150円にしてくれないかと願い出た。しかし、このとき会長は首をタテには振らなかった。
ところがその後、面白いことが起こった。
同じ時期、例の食堂部門の外注問題が私たちを悩ませていたのだが、その渦中の女性従業員の一人(私を最も勢いよく糾弾したあのSさんだ)が、地主会長の近所に住んでいたのだ。そのSさんと会長がたまたま路上で顔を合わせ、会長が挨拶代わりに東松山CCの経営状態について聞いてみたらしい。するとそのとき、彼女はこう答えたと言う。
「もう大変ですよ。外注会社が入ってくれば、私なんかクビですよ。まったく…」
なんと、この怒り半ばの答えによって、初めて会長は私の言っていることに信憑性を得たのだ。これは幸運と言うべきなのか。あるいは、その女性従業員に感謝すべきことなのか。
地主会長からはすぐに連絡があり、「地主をみんな集めるので、伊室さんから地代について説明してくれ。私の一存では決められるものではないから」と言うのである。
そして私は、集まってくれた地主たちの前で、会長に訴えたと同じ内容のことを、より具体的な実例を挙げて話した。実際、埼玉県内の他のいくつものゴルフ場に、外資の経営者が入っており、それらのゴルフ場では経費の徹底的な合理化が推進されて、地代の値下げ再契約がされる状態だった。
「何とかゴルフ場経営が継続できるように、地代を下げていただきたいのです。なにとぞ、ご協力をお願いいたします」
私は丁寧に頭を下げた。すると、地主会長からも一言があった。
「どうだろうか。ここは一つ、話に乗ってあげようと思うんだが。会社を潰したんじゃあ、元も子もないしな」
おそらく、会長のこの言葉が最終的に地主たちの背中を押してくれることになったのだろう。最初は腕組みをしながら渋い顔をしていたほとんどの地主たちが、うなづいてくれたのだ。この瞬間、満期前にもかかわらず、1㎡当たり150円というレートで、地代値下げが承認されたのである。そして20年の満期更改期には1㎡当たり100円で決着し、固定費削減に大きく寄与することになった。

東松山CCについては、その後、運営会社の社長も理事長も他の人に引き継ぎ、会長職(平成15年6月から1年間のみ)を経て一度だけ名誉顧問という肩書をいただいたが、運営会社も理事会もより若い世代に任せるべきだという考えから、もっぱらプレーを楽しむ立場に専念することにしている。
理事長時代と二度の社長時代を振り返ると、私のなかに夏坂健さんによるゴルフ理念が住み着いていて、「本物のゴルフのできる本物のゴルフ場」のイメージを追いかけながら、ただ一生懸命やってきたという印象だけが残る。“世俗”的な欲を追求していたのでは、決して続けられる仕事ではなかっただろう(実際にすべてボランティアである)。
その結果として、さまざまな人間関係の壁にぶつかりながらも、バブル期の後遺症が治療でき、ゴルフ場全体もきれいになって、何とか健全なゴルフ場経営ができる状態にまでは持っていくことができたかなという思いはある。
そしてもう一つ言えることは、ある程度の年齢を重ねてからは、その年齢に相応しい経験知を活かした仕事のやり方があるものだという、私なりの発見があったということだ。その意味では、安田火災の関連会社を辞めてからも仕事にやり甲斐を与え続けてくれたこと、また、まだ余力のあるうちに物事に一生懸命になれる機会を与えてくれたことについて、私は東松山CCに大いに感謝しているのである。
「へんこつ隊長」後藤四郎さん
その数奇な軍隊遍歴
平成17(2005)年4月、私は『写真で綴る 後藤四郎さんの軌跡』という冊子(A4判90ページ)を執筆・編集した。発行は「みはた会」という団体である。
この後藤四郎さんは、先の大戦の敗戦時、歩兵第321連隊連隊長を務めていた人だ(最終階級は中佐)。そのとき軍命によって「焼き捨てろ」と言われた軍旗を独自に秘匿し、解体する日本陸軍の形見として戦後もこれを保管し続けた。その後、この軍旗の下に旧連隊の有志が集まり、後藤さんを中心とした懇親の会を催し続ける。この会が「みはた会(御旗会)」である。
しかし、こんな概略の説明だけでは、後藤四郎という人物の将校としての数奇な軍歴もその魅力的な人柄も伝わらない。後藤さんと私との出会いと彼の戦前・戦後の足跡をいくらか述べておきたいと思う。

私が後藤四郎さんと出会ったのは、偕行社という公益財団法人の同好会の一つ、偕行ゴルフ会が最初だった。偕行社というのは、旧陸軍の将校や軍学校生徒、軍属高等官、また戦後の陸上自衛隊の元幹部などによる親睦団体である。
平成5(1993)年10月に武蔵カントリークラブで行われた偕行ゴルフ会の実行委員長を仰せつかっていた私は、プレー後の会食会で参加者のなかでは最高齢者である後藤四郎さんに乾杯の挨拶をお願いしようと思い、マイクを持って彼の席に近づいた。ところが、「マイクは要らない!」と眼下に一喝されてしまったのである。会場に響きわたったその鋭い語気は、未だに私の耳に残っている。
このとき後藤さん85歳(明治41年生まれ)。いま(平成27年現在)の私より2歳年下である。
恥ずかしながら、私はその矍鑠たる年長者がどんな人物であるのか、それほど詳しく知っていたわけではない。偕行社の他のメンバーから、陸軍士官学校41期であり、私の20年先輩であることを伝え聞いていた程度だった。
しかし私は、このゴルフ会においてひときわ異彩を放っていたその存在感に惹きつけられ、興味をもってしまったのである。
そして後日、後藤さんが3冊の本を上梓していることを知った。『陸軍へんこつ隊長物語』(牧内節夫氏編)、『〈続〉陸軍へんこつ隊長物語』(同)、『軍命違反「軍旗ハ焼カズ」―陸軍へんこつ隊長手記』(植田弘氏構成)である(いずれも毎日新聞社刊)。私はそのなかに、驚くほど数奇な経歴を重ねた一人の魅力ある陸軍将校の姿を発見するのである。

大分県中津市出身の後藤四郎さんは、大正11(1922)年4月、熊本陸軍幼年学校に入学している。そして大正14(1925)年に陸軍士官学校予科(のち陸軍予科士官学校)に進学、続いて本科に進み、昭和4(1929)年、小倉連隊の隊付少尉として任官された。その後、将校や下士官に対してより高度な専門教育を受けさせる陸軍戸山学校(東京)に派遣され、半年ほど訓練を受けている。
後藤さんが戸山学校に行っている頃、士官学校の同期生の一人から、若松町の某旅館で同期の集まりがあるから来ないかという誘いを受けた。後藤さんは何の疑いもなく出かけて行くのだが、実はそれは桜会による秘密の集会だったのである。
桜会とはどのような団体なのか?
後藤さんが任官された昭和4年は、ニューヨーク証券取引所における株の大暴落に起因する世界大恐慌が始まった年である。その直後から大不況と大凶作の波が日本全土に押し寄せる。
とりわけ東北地方の農村では、女子は身売りを強いられ、次男三男は軍隊に行かされる、つまり“口減らし”のような光景が至るところで見られた。まさに「おしん」の世界だ。
東北の農村部から入営してくる兵隊には世間ずれしていない実直な人間が多い。だから、自分が口減らしのために軍隊に入れられたとしても、少ない給料のなかから極貧の実家に仕送りをする。そんな光景を頻繁に目にする青年将校たちは、兵隊たちと家族の事情を察し、黙って自分の給料から足し前をしてやるなどということがあった。
しかし、「こんなことはやはりおかしい、何かが間違っている」と考え、政府への批判を強める将校も増えていく。そのような状況から生まれた超国家的な政治結社の一つに桜会があった。
橋本欣五郎中佐、長勇少佐らによる参謀本部付きの将校と右翼思想家大川周明らが結びつき、政党政治の腐敗を糾し、軍事政権の樹立によって国家改造をめざす結社である。その主要メンバーたちは昭和6(1931)年に昭和維新を唱えるクーデター未遂事件を二度まで起こした(三月事件、十月事件)。しかし計画に関与した主たる人間のなかに陸軍首脳部も含まれ、また陸軍内部の権力闘争も絡んでくるため、二つの事件後の措置は曖昧なままにされ、橋本中佐や長少佐らは軽微な処分で済まされたのである。
ところが、東京憲兵隊は密かに桜会メンバーのブラックリストを作成していた。このブラックリストに乗せられた人間は要注意人物として海外へと追放になってしまう。実際には何も知らずに集会に参加した後藤四郎さんも、このリストに載せられ、桜会の事件に連座したという嫌疑がかけられてしまった。そして昭和8(1933)年11月、独立守備隊長として満州の奥地へと送られてしまうのである。これは懲罰的な左遷という性格を持った異動である。
ここから後藤四郎さんの戦地での姿を記すことになるが、彼の武勲だけを語ることがここでの目的ではない。ただ、後藤さんにおけるその後の重要な出来事の前哨として、彼の戦前の数奇な足跡を総覧しておきたいのである。
さて、満州独立守備隊長として着任した後藤さんの主な任務は、南満州鉄道(新建設地域を含む)と居留民地の警護だ。厳しい自然環境の下で、匪賊や抗日ゲリラが出没し治安混迷を極める広大な地域で6年間も勤務する。
その間の苛烈な戦線下において、後藤さんは、教育の機会に恵まれなかった兵隊たちに難解な用語ばかりの軍律で統率を維持することはきないと考えた。軍隊の厳しい上下関係であっても、「子を思う親の心」「親を思う子の心」というものが不可欠だと平明な言葉で部下たちに解き、強圧的な態度で部下に接することはなかったと言う。部下に対するこの独特な教育方法は、関東軍の上層部からは批判を浴びたが、兵隊思いの後藤さんは自分のやり方を貫き通したのである。

満州の人たちに対しても、後藤さんは寛容であり優しかった。きわめて貧しい状態にあった赴任地の周辺住民を集め、「集団部落」というコミュニティをつくり、満鉄の本社や支社からの寄付による衣類や日用品を子どもたちに配布するなど、慈善活動と言えるようなことを積極的に行っていた。
そんな後藤さんは部下将兵から「へんこつ隊長」という愛称で呼ばれることがあった。その「へんこつ」は、九州から中国地方の方言でいう「偏屈」をさす。つまり、自分の正義感と意志とを貫き通す、「偏屈=頑固者」の隊長という意味だ。関東軍の幹部からも睨まれ、他の部隊とも違う満州人への接し方を貫いた後藤さんは、まさに「へんこつ」の典型として部下将兵から慕われていたのだった。
さらに最前線へ送られる後藤少尉
親授された軍旗への思い
しかし、そんな後藤さんに再び過酷な運命が押し寄せる。
昭和11(1936)年2月26日、はるか離れた帝都であの二・二六事件が起こったのだ。満州にいた後藤さんがこの事件に関与できるはずもなかったが、かつて桜会関連のブラックリストに名を載せられたことが災いして、時の関東軍憲兵隊司令官にマークされ、出頭を命じられた。そして、大した取り調べもないまま、証拠も明らかにされず、「二・二六事件に関係ありと疑わるるが如き言動ありたるにより」という一方的な理由で重謹慎30日の処罰を受け、さらに理不尽な3つの処分内容を宣告されてしまうのである。
曰く、「陸軍大学校の受験禁止、二期進級停止、内地に帰還を許さず」、この3つである。
この無体とも言える科罰を言い渡した関東軍憲兵隊司令官こそ、のちに陸軍大臣、そして内閣総理大臣となる東條英機少将(当時)だった。陸軍内の統制派の中心にいた東條少将には、二・二六事件に決起した皇道派の将校たちに少しでも関係がありそうな将校を一掃したいと言う思惑があったとされる。上記の三つの処罰内容を見れば、皇道派と思しき将校の将来を抹殺し、国外で命を消耗させようとする異様な意図がはっきりとわかる。
しかし後藤さんは、心情的に皇道派の考え(国内の貧困を一掃したいなど)にいくらか共鳴するところがあったとしても、軍内部の権力闘争に加担するような人間ではなかった。それどころか、後藤さんに見られたのは、満州における自分に科せられた任務を脇目も振らず忠実に遂行する勇猛果敢な帝国陸軍軍人の姿そのものだった。
この処分後、後藤さんは満州国境守備隊長に転属(これにも懲罰的な意味合いがあった)。150m先にいるソ連兵と向き合う苛烈な最前線で、危うい生死のふちを何度も行き来するような勇姿を自ら率先して示していく(この頃中尉に昇級)。その「へんこつ隊長」ぶりによって、国境守備隊に送られて荒くれていた兵隊たちを完全に心服させたのである(これには部下たちの証言がある)。

昭和15(1940)年には揚子江(長江)最上流の最前線、宣昌に大隊長(大尉に昇級)として転戦し、二度の熾烈な作戦に参加。その際、部下たちが次々に戦死するなかで、後藤さんは膝に銃槍を受けて後送されてしまう。
このとき指揮下にあった連隊の一つ、歩兵第58連隊は、その後ビルマのインパールへ転進し、その大部分の中隊は玉砕した。このことは後藤さんの脳裏から決して離れることはなく、インパールの野戦で屍をさらしたかつての部下たちのことを顧みて、「自分だけ墓に入るわけにはいかない」という思いを強くしたと言う。
その後、負傷した後藤さんは、漢口、南京、上海の各野戦病院を転々とし、宇品を経て内地に送還された。かつて関東憲兵隊から二期の進級停止を宣告されていた後藤さんは、このときようやく陸軍少佐になることができた。実際、少佐への昇級は士官学校同期のうちでも一番遅かった。
9年間、満州・中国に追いやられていた後藤さんは、膝の傷が癒えたのち、しばらく大本営陸軍報道部に勤務となるが、このときすでに昭和18年。報道部であればこそ、日ごとに伝わる戦局の厳しさは事実として知ることができた。
そして昭和20年6月、市民を巻き込み、熾烈の限りを尽くした沖縄戦が終わろうとしているとき、後藤さんは本土防衛のために新設された歩兵第321連隊長に選任され、同時に中佐に昇進した。駐屯地は広島市の東、原村というところだった。
新設の連隊には、新たな軍旗が授与されることになっている。そこで7月23日、連隊長である後藤さんは上京し、部下の旗手(S少尉)を従えて宮中に参内。軍旗親授式に臨むことになった。その日の早朝、後藤さんは沐浴し、心身を清めている。
その軍旗親授の場面を後藤さんの手記から引用してみよう。
「(前略)私はS少尉を従え、玉座正面の入り口に進んだ。かねて玉座の両面には各皇族殿下、諸将軍が侍立していると聞いていた。が、緊張しきった私の双眸に映ったものは、ただ正面の陛下御一人のお姿だけだった。(中略)陛下御手ずから真新しい軍旗が…相当の重量感を伴って私の双手に移るとき、陛下のお手先がかすかに私の手に触れた。瞬間全身に電流が流れたかのように感じられた。数歩後退して軍旗をS少尉に手渡し、再び陛下に正面すると、朗々とした玉音が熟しきった私の耳朶を打った」(S少尉は本名記載、他は本文のママ)
ここでの玉音、すなわち天皇の言葉はこうだ。
「歩兵第321連隊ノ為軍旗一旗ヲ授ク 汝軍人等協力同心シテ益々威武ヲ宣揚シ 我ガ帝国ヲ保護セヨ」
これに対して、後藤さんは奉答書に書かれた次の言葉をもって謹んで応える。
「敬テ明勅ヲ奉ズ 臣等死力ヲツクシ 誓ッテ帝国ヲ保護セン」
(引用は『私はこうして軍旗を守った』後藤四郎/昭和47年2月記による)
ここに語られているのは、当時の帝国軍人にとって、いかに軍旗が“大元帥”たる天皇の威光と直結したものであるかを示す鮮烈な記憶だ。後藤さんの心身にも、この感覚は思いのほか深く刻み込まれている。
ところが、宮中での軍旗親授から1か月も経たないうちに、広島に原爆が投下されてしまう。駐屯する原村から20km程度しか離れていない後藤さんの第321連隊は、取るものも取りあえず急きょ救護に向かった。そして自らも放射能に被曝しながら、軍人、市民の別け隔てなく救援活動を行い、その一方で屍体の収容、焼け跡の整備のために奮闘し続けたのである。
当時は、当然のことながら、誰も放射能についての知識はなかった。後年、第321連隊の将兵たちには、後藤さんも含め、被曝手帳を交付されたが、なかには原爆症のような症状を発症した人もいる。
その9日後、8月15日が来たのである。
ここでようやく、後藤四郎さんの戦後における稀有な意味合いが見えてくる。戦前と戦後を分けるはずのこの日が来ても、後藤四郎という人の軍旗に対する陸軍中佐としての意識は強固に持続されることになるからだ。
いわゆる「終戦の詔勅」ののち、日本中の軍人たちが底知れぬ葛藤の淵に追いやられた。
例えば東京では、陸軍省幕僚と近衛師団参謀の将校たちを中心としたクーデター未遂事件(いわゆる「宮城事件」)が起きた。また、阿南惟幾陸軍大臣を筆頭に、何人もの軍人が自決し、あるいはまた、敗戦を認めない将校たちの徹底抗戦に向けた行動はしばらくの間、続いた。
陸軍予科士官学校在学中の私ですら、現実の戦地経験こそなかったが、来るべき本土決戦に備えるべく、仲間とともに決起しようとしたくらいである(第1章 第1部参照)。
その一方で、ほとんどの軍人・兵隊が大きな失意と葛藤のうちに武装解除に応じるという道を選ぶことになる。後藤四郎中佐も表向きは同様だったが、その後の思いと行動が違った。
その状況下、後藤さんが軍旗を拝受して1か月目の8月23日、陸軍省では最後の参謀会議が開かれた。その議題の一つに軍旗処理の問題があった。
参謀会議の結論はこうだった。軍の魂である軍旗は、本来、運命をともにするのが陸軍の伝統精神である。しかし、「御聖断」を下された大元帥への誤った忠誠心によって集団自決を図る連隊が出ないよう、「師団司令部に全軍旗を集め、師団長立ち会いの下で奉焼すべし」というのである。占領軍の手に渡らないようにするということも、重要な理由の一つだった。
軍命には従えない
そして軍旗は秘匿された
数日後、その参謀会議の決定(軍命)が第321連隊にも通達されたものの、後藤さんはどうしてもそれには従えないという強い葛藤に襲われる。
「陛下の御手の温もりを感じつつ親授された軍旗を、どうして手放せよう」
戦後の世評はさまざまだとしても、ポツダム宣言受諾直後のこの段階において、日本陸軍は正義の軍であったと、後藤さんは固く信じていた。少なくとも自分は、軍人として恥じない行いを貫いてきたと確信するからだ。とすれば、軍旗をむざむざと灰燼に帰していいわけがない。
そこで後藤さんは、通常の帝国軍人ならば決して思いもつかないであろう重大な決意をする。軍旗を自分の責任で秘匿しようと言うのである。軍人生活の最終段階で、後藤さんは敢えて軍命に反する行動を摂ったのだ。
後藤さんは、本来は師団司令部に集めて焼かなければならない軍旗を、自分の連隊で奉焼する旨を師団長に伝えた。師団長は普段から信頼の厚い後藤さんのこの申し入れを許可したのである。
そして腹心の部下、I少尉の協力を得て、その旗竿だけを軍旗箱に入れ、事情を知らない連隊将兵の見守るなか、これを焼却した。無論、この軍旗なき軍旗箱は、たちどころに燃え上がってしまう。
残された軍旗と竿頭の菊のご紋章は別の小箱に入れられ、信頼するI少尉に託されて山口県の周防にある日本神社(後藤さんが敬仰する神道系の神社)に届けられた。そこで2年の間保管されたのち、長崎の後藤さん宅に移され、以後4年の間、丁重に秘匿されることになる。
昭和26年9月、サンフランシスコ講和条約が締結され、国際法上の日本国の主権が回復された。軍旗はもはや占領軍の手に渡る可能性もなく、秘匿しておく必要もなくなった。
そこで4年後の昭和30(1955)年7月23日、奇しくもあの軍旗親授式から10年後の同じ日、かつての第321連隊有志が後藤さん宅に集合し、軍旗祭を催したのである。
その後、この軍旗のことが知られるようになり、昭和34年8月のNHKのクイズ番組、「私の秘密」に取り上げられることになった。しかし、「私は軍旗を持っています」という後藤さんの“秘密”は、どの回答者も正解することができなかった。かつての帝国軍人が軍命に反して軍旗を隠し持っていたなどとは、誰も想像できなかったからである。
さらに昭和38年、靖国神社から要請があり、軍旗を奉納してほしい旨が伝えられたが、当時の後藤さんの判断によって、奉納ではなく貸与するということになった。戦後の靖国神社はすでに国家機関ではなく、私的な一宗教法人であるという後藤さんの認識が働いたからだ。
ただ、このとき軍旗の存在を新聞紙上で知った戦友数十人が靖国神社に集まり、「軍旗を奉じた戦後初の部隊参拝」が行われた。これがその後の「みはた会」誕生へとつながっていく。
しかしずっと後年、平成5(1993)年には、軍旗は正式に靖国神社に奉納されることになった。この時の後藤さんの考えとして、靖国神社はすでに「国家護持」の立場にはなく、「国民護持」に徹する宗教法人であるべきだということがある。
もしこの「国民護持」が目的の神社であるならば、天皇に軍旗をお返しする代わりに、祀られている英霊(国民としての軍人・将兵の霊)に軍旗を手渡し、後藤さん自らの軍旗護持の任務を完了させるというのが、靖国神社への軍旗奉納の趣旨だった。
平成5(1993)年10月の偕行ゴルフ会で出会って以来、私はすっかり後藤四郎という人に魅せられてしまった。その理由は、上記の後藤さんの波乱に満ちた人生とその後の軍旗の運命について読んでいただければおわかりいただけるだろう。
もっとも、世代によっては理解いただけないことがあるかもしれない。しかし、私と同じかそれ以上の世代、とりわけ陸軍幼年学校や士官学校といった軍学校を経験し、あるいは軍隊経験のある世代なら、軍人にとっての軍旗というものにどれほど重く国家というものの意味が付与されているか、実感としてわかっていただけるはずだ。
それは天皇親率の軍隊を象徴する重みである。しかし、その中身を言葉化することはたやすいことではない。言わば旧帝国軍人に完全に身体化され、血肉になりきり、骨身に染みこんでいるものだからだ。若い世代から批判があろうと、この身体にまとわりついた心情を伝えきることは至難の技だとすら思える。
その後、旧第321連隊有志以外にも軍旗の存在を知る人は日ごとに増え、後藤さんが上梓した本を読んで心を動かされた人たちも「みはた会」に加わった。偕行ゴルフ会をはじめとする会の行事はますます盛大になっていくなかで、私も後発の会員として参加し、後藤さんの身近でその波乱に満ちた経験をつぶさに伺うことができたのである。
そしてその都度、齢を重ねるごとにむしろ魅力的な生き方を示す後藤さんの姿を愛用のライカM6に収め、ついに撮り貯めた写真をメインにした『写真で綴る 後藤四郎さんの軌跡』を編集・執筆することになったのである。

それは、戦争への全体的な歴史評価とは別次元において、戦争の個々の場面で自分なりの信念と正義とを貫き生きた一人の帝国軍人その人と向き合ったとき、私が感じえた尊敬を形にしたものだ。
戦争がいかに過酷であり、残酷であり、そして悲惨なものであるかは、戦時下を生きた人間としてわかっているつもりだ。しかし、それらの現実を抽象的かつ十把一絡げに嫌って遠ざけるのではなく、命を賭して過酷で残酷で悲惨な戦火のなかで死闘を繰り返さざるをえなかった人間が、どのような考えと判断によってその具体的な現実を生き抜いてきたか、それを真摯に傾聴することは重要である。
陸軍幼年学校・予科士官学校で将校になるための研鑽を重ねながら、実際には戦地に赴くことのなかった私にとって、後藤四郎さんの戦中・敗戦時・戦後における数奇な生き方の足跡を知ることは、同時代を生きた者としてきわめて重要な実感的な追体験となった。私は後藤四郎さんに導かれて、自分の戦争体験を改めて見直し続ける必要を感じる。
歴史の全てがわかっているわけではない以上、新たな証言や資料によって、歴史は常に未来に向かって更新されていくものなのである。
後藤四郎さんは、平成17(2005)年も明けた1月20日、享年97歳という天寿を全うされ逝去。まさに大往生である。その新年の句が、辞世となった。
百歳も 間近になりぬ 初日の出
何と大らかで寛容な心境だろう。私は後藤さんの晩年の笑顔とともに、この句を思い起こすことがある。後藤さんに見えているものは夕陽ではなく、いつも「日の出」なのだ。この前向きの生き方にこそ学ぶべきものがある。
中国大陸で百戦を生き抜き、さらに天皇親率の軍隊を象徴する軍旗を秘匿した人物の最期の発露が、このような穏やかなものであるとは、それこそ誰が想像できただろう。しかしながら、そもそも後藤四郎さんの魂の根底にこの穏やかさの土壌があったればこそ、何事にも誠実に向き合い、そして何事にも動じない後藤さんらしい生があったのだと思う。
軍人になるための教育を受けた私にとって、自分ならどう生きただろうかと自問するための一人の尊敬するモデルとして、「へんこつ隊長」たる後藤四郎さんは、ずっと私のなかに生きていた。しかし一方で、私はこの後藤さんの辞世に表されている寛容さと大らかさを、自分のなかにもっと育んでいきたいと思っている。
小倉寛太郎との特筆すべき再会
彼は別人として私の前に現れた
これまでの人生で培われた人との“つながり”は数えようもない。友人、知人、先輩に導かれながら私はどこに赴くのだろうと、ときどき、そう思うことがある。
もちろん私にも意志はある。しかし私には、愉快な出会いや楽しい出来事の方へと引き寄せられながら生きてきたようなところがある。その幸運には感謝してもしきれない。
齢を重ねた人間は、「キョウイク」と「キョウヨウ」があれば、前向きに、かつ元気に生きられるというものだ。
勘違いされては困る。「今日行くところ」と「今日用がある」ということの大切さを言っているのだ(これは千葉大学名誉教授の多湖輝さんのご説と聞く)。幸いなことに、よい年になったいまでも、私は「行くところ」と「用事」には実に恵まれている。その大半は、まさに友人、知人、先輩たちとの“つながり”によって導かれるものだ。
ここで私にとって特筆すべき一つの“再会”について述べておきたい。これも例によって、時間軸をさかのぼりながら記すことになる。
かつて、昭和52(1977)年からの5年間、私は安田火災の名古屋支店長として勤務していた(第2章 第2部参照)。その頃、名古屋西ロータリークラブに入会していたのだが、そこで同じように東京から転勤してきた日本航空の名古屋支店長(当時)、Mさんと親しくなった。明治の元勲の一人、総理大臣を二度務めた松方正義のひ孫に当たる方だ。
私は5年間で東京に戻ったが、Mさんはそれよりも長く名古屋支店に勤務し、最終的には当初の目的だった国際線の名古屋就航を実現するという大仕事を果たした。これは航空ビジネスの世界ではよく知られた逸話だと聞く。
私たちは帰京後も、同時期に名古屋生活を共有した仲間で集まって「名遊会」という会をつくり、親交を温めてきた。現在も楽しい集いや小旅行を続けている。もちろんMさんもその主要メンバーである。

平成10(1998)年5月、Mさんが「名遊会」の幹事のとき、那須の別荘「万歳閣」へお招きいただいたことがある。
明治36(1903)年にMさんの曽祖父、松方正義が建てたという「万歳閣」は、明治の佇まいを色濃く残した洋風建築で、私たち会のメンバーはすっかり気に入ってしまった。そのために翌年の秋にも「万歳閣」で会の集いを開くことになり、2年連続して那須の空気を満喫することになった。
その一夜、Mさんと親しく歓談しているとき、私はふと思いついてこんな質問をしてみた。
「そう言えば、日本航空では思い出す人がいるんですよ。小倉寛太郎さんをご存知ですか?」
この名前を出した瞬間、Mさんの顔に緊張が走り、語気強くこう聞き返された。
「君、どうして小倉寛太郎を知っているんだ?」
私は何気なく聞いたつもりだったが、Mさんの返答の仕方には却ってこちらが驚いた。しかし、「さもあろう」とすぐに合点がいった。
1960年代の日本航空で労働組合委員長を務めた小倉さんは、当時の経営陣と厳しく対立し、日本航空で最初のストライキを敢行した組合指導者だった。そのため、その後の左遷人事によって、カラチ、テヘラン、ナイロビへと次々に飛ばされてしまう。社内規定を大きく超える10年以上にわたる海外勤務などの様子は、小倉さんがモデルとなった小説、山崎豊子の『沈まぬ太陽』に詳しく描写されている。
そんな小倉さんを、日本航空の経営側に名を連ねるMさんが知らないわけがない。かつては経営陣を脅かす“けしからん存在”だったのである。
しかし、Mさんにとっても、そんな小倉さんのイメージは過去のものにすぎなかった。私の問いかけに一瞬だけ顔色が変わったが、この当時には登山という共通の趣味を通じて小倉さんとは親しく交遊した仲だったのだ。
それを聞いて私も安心し、小倉さんとは同じ大学の同期生であり(第1章 第2部参照)、安田火災に入社してからも、同業他社の組合活動をしていた彼とちょっとした接点をもったことがあるという昔話を披露した(第2章 第1部参照)。
するとMさんは、そこに居合わせたサバンナクラブのメンバーで元日本航空社員のHさんに向かって、こう言うのだった。
「H君はサバンナクラブの会員だったね。伊室さんを例会に連れて行って、小倉君に会わせてあげてくれないか」
こんなやりとりがあった翌年(2000年)の2月、私はHさんのゲストとして、初めてサバンナクラブの例会に出席し、そこで小倉寛太郎さんとの再会を果たすことができたのである。
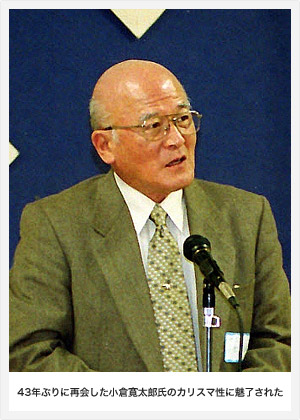
サバンナクラブは、東アフリカの自然と人、文化を愛する人たちが交流し、親交を温める会だ。昭和56(1976)年に動物作家の戸川幸夫さん(初代会長)や小倉寛太郎さんなどによって設立。以来、サバンナについての知識や理解を深める例会や会員によるサバンナ体験などの報告会を催し、東アフリカ諸国への支援を含めた多様な活動を行っている。私が小倉さんと再会したこの当時、彼が事務局長を務めていた。
サバンナクラブ事務局長として例会を仕切っていたその姿は凛として立派だった。東大時代に駒場祭の初代委員長となり、東大初の大学生協をつくり、卒業してからも組合運動や労働運動に一生懸命で、日本航空でも経営者たちとの闘争を繰り返し、その後も左遷人事で苦労を重ねてきた彼からは想像もできない、別人として私の前に現れた。
人に対するにきわめて温厚であり、人間として成熟しており、それでいて集団を前にしたときの統率力を感じる。そのうえ話術に長け、話が実に面白い。そんな存在なのだ。私はこのときの小倉寛太郎という人間に、とてつもないオーラを感じ、再会の挨拶を交わす前からその姿に魅了されてしまった。
例会の会食後、Hさんが小倉さんの席まで連れて行ってくださった。私はおもむろに挨拶する。
「伊室です、覚えていますか? 僕らが東大のグランドで野球をやっているとき、小倉さんは隣でサッカーに興じていたでしょ。昭和28年卒業ですから、もう47年も経っているわけですが…」
「もちろん、覚えてますよ。その何年か後に、全損保の給与問題のときにもお会いしたでしょ。となると、43年ぶりぐらいじゃないですか? 懐かしいなぁ」
全損保とは、全損害保険労働組合のことだ。昭和32(1957)年、損保業界全体で給与体系の改定問題が持ち上がったとき、小倉さんは大学卒業後4年にしてその全損保の地方協議会書記長として頭角を表し、各損保会社の組合に出入りしたのである。そのときまだ入社4年目の私と小倉さんが偶然に顔を合わせたために、安田火災社内で危うい立場に追い込まれそうになったという過去がある(第2章 第1部参照)。
しかし、そんなことはこのときには既に笑い話だ。43年という時間がお互いの人生を少しだけ遠ざけ、丁寧語で会話するだけの距離が生じていたものの、それでも二人して懐かしい旧友のことや思い出話に花を咲かせた。
サバンナクラブへの入会
2年間で消えてしまった再会の喜び
「伊室さん、写真をやるんですって? さっき小耳に挟んだんだけど」
小倉さんはいきなり話を向けてきた。
「ええ、学生時代から写真は撮っていたんですが、サラリーマン時代はせいぜい日頃のスナップぐらいしか撮れませんでしたね。安田火災を退職してから少し時間もできたので、ちょっと根性を入れ直してやっています。あちこち海外を旅行して、風景写真を撮っているんですよ」
この前年とこの年、私は妻と連れ立ってアラスカを旅してきたばかりだった。その際、愛用のライカM6を駆使して、大自然をファインダーで捉えてみたのだが、必ずしも満足のいく写真だけが撮れていたわけではなかった。
「特にマッキンリーでは見晴台からしか撮影できなくてね、どう撮っても絵葉書と同じような写真になっちゃうんですよ。マッキンリーの前景に、カリブーだとかグリズリーだとか、自然の動物たちが行き交うところでも撮れれば、いい絵になったと思うんですけど」
私がそう言うと、小倉さんはすかざす、目を輝かせてこう言うのだった。
「そういうことなら伊室さん、ぜひアフリカへ行くといい。群れをなしてゆったりと行く象たちを前景に、氷河を頂くキリマンジャロを撮るなんていうのはどうですか? 今年の夏、早速、行きませんか?」
笑みを浮かべながら話す小倉さんのお誘いを拒む理由は全くなかった。それどころか、その話に出てくるサバンナのリアルな光景は、最早、私の心をつかんでしまっていた。
そしてその年(平成12/2000年)の8月、私は小倉さんに伴われて、初めてケニアサファリへと出かけて行ったのである。
ここに1枚の写真がある。ケニア北部、シャバ国立保護区のサンブルでのサファリで撮った、2頭のクリップスプリンガーの写真だ。

この子鹿のようにかわいい動物は、蹄の先がクリップのように2つに割れている(偶蹄目ウシ科に分類される)。そのクリップのように分かれた小さな蹄で岩をつかみ、岩から岩へと跳ねて移動することができる。そのうえ、足の接地面が小さいので、狭い足場でもずっと立っていることが可能だ。その優美な姿から、“岩山のバレリーナ”とも呼ばれる。
私がこのクリップスプリンガーをカメラに収めることができたのは、サファリの最中、小倉さんに促されるままにとある岩陰に30分ほど待っていたときのことだ。ただ漫然とファインダーを覗いていると、よく見なければ見逃しそうな岩場の陰に2頭の可愛い動物が見えた。そこで私は夢中でシャッターを切ったのだ。クリップスプリンガーは岩陰とほぼ同系色なので、「危うく見逃すところだった。撮れたのはラッキー!」と、そのときの私は思っていた。
ロッジに戻ると、得意げにこの話をサファリ仲間に吹聴する私。
「いやー、今日はついていたよ。偶然にもクリップスプリンガーが撮れたんだから」
すると小倉さんは笑顔で私を諭してくれた。
「伊室さん、ラッキーだけではあれは撮れないのですよ。あそこにクリップスプリンガーが棲んでいることを知らなければ、ほとんどの人は見過ごしてしまいますからね」
私はハッとして、偶然に撮れたと思い込んでいた自分の不明を恥じた。実は小倉さんは綿密な計画を立て、しかも1週間前に事前に下見までしてくれていたのだ。
聞けば、クリップスプリンガーは夜行性で、昼間はほとんど岩陰などで休息しているという。そのことを知っていた小倉さんは、私が撮影に成功するように、最適な時間に最適な場所まで連れて行ってくれたのである。
さすがにケニア在住7年半、3,000日のサファリ歴を持つ“スペシャル・ガイド”ならではの、サファリ初心者への配慮だった。
小倉さんは、サバンナクラブ設立以前から、アフリカ滞在中はもちろん、日本に帰ってきても、その魅力に引きつけられてアフリカを訪れる人たちに情報提供をしたり、渡航の手伝いをしたりしていたと聞く。大学の同級生だった映画監督の山田洋次さんや羽仁進さん、渥美清さん、杉村春子さん、八千草薫さん、いかりや長介さんといった面々も、かつてナイロビ支店長時代の小倉邸をよく訪れたそうだ。とりわけ寅さんこと渥美清さんは、映画の撮影でアフリカでの長期ロケを経験して以来、サバンナの常連になっていた。
サバンナクラブは、そんな世話好きの小倉さんのキャラクターとプロデュース能力がいかんなく発揮された愉快な会として成長していった。サファリ初体験の私が、帰国後も小倉さんに会える例会や報告会が楽しみになっていったのは、彼の魅力のせいでもある。
それとともに私は、小倉さんの事務局長としての行動力に目を見張った。ただサファリを楽しむという目的のために、そしてその目的を大事にするための発想とアイデアがどんどん生まれ、それらを実行していくのである。
その小倉さんから、平成14(2002)年の5月に突然の電話があった。この年の夏にはもう一度ケニアサファリに行く計画をしてくださっていたので、その話かと思って受話器を取った。ところが、小倉さんは全く別の話を切り出したのだ。
「伊室さん、僕、ガンなんだ。肺ガン。残念だけど、今年のサファリは一緒に行けないな」
もちろん私は驚いたが、冷静を装ってこう言うしかなかった。
「肺ガンなんて治るさ。大丈夫。サファリ、また連れて行ってよ。一緒に行こうよ」
サバンナクラブ入会後まだ2年しか経っていない私だったが、このときには大学時代の同級生のような間柄に戻っていて、2人はタメ口で話すようになっていた。
しかし、私の2回目のケニアサファリに小倉さんは同行できず、やや寂しいものに終わってしまった。そのとき、サファリ初心者の私には、サバンナクラブのサファリツアーにおいて小倉寛太郎という人の存在がいかに大きいものであるかを思い知った。
「オグラさんはどうしましたか?」、「オグラさんはいつ来ますか?」、「オグラさん、大丈夫ですか?」と、行く先々でケニアの人たちに聞かれるのである。それに対して私は、「大丈夫、今度来るときには、小倉さん、一緒に連れてくるから」と確信もないのに言い、彼らを一時だけ安心させるしか手立てがなかった。
しかし、私は帰国後に小倉さんの容態が思わしくないことを知った。そしてその年の10月2日、小倉寛太郎は肺ガンのため、72年の生涯を閉じたのである。

せっかく43年ぶりに再会を果たし、ようやくタメ口を聞けるような仲に戻れたのに、その間柄はたった2年で終えてしまった。もうあんなに面白い話が聞けないのか、もうあんなに充実したサファリはできなくなるのではないか…。私は初めて行ったケニアサファリの写真を目の前にして、とてつもなく貴重な友人を失ったのだという思いを強くしていた。
楽しみを分かち合うサバンナクラブ
事務局長を仰せつかる
「一旦、東アフリカの魅力にとりつかれると、東アフリカについて、やたらにしゃべりたくなります。しかし、相手がいつも耳を傾けてくれるとは限りません。だから、心おきなく東アフリカについて、熱を上げ、しゃべりまくり、また、耳を傾ける仲間が欲しくなります。サバンナクラブは、このような願いを実現するための集まりです。そうして、共通の郷愁の場である東アフリカについて、知識を深め合う集まりです」
これは、昭和51(1976)年のサバンナクラブ発足時、小倉寛太郎さんが呼びかけた趣意書のなかの言葉だ。この平明かつ軽妙な語り口のなかに、小倉さんの人格とものの考え方がはっきりと込められている。
それは、ものごとの情報や知識は独占するべきではなく、それらを共有することによって、その先にある楽しみまでも共有しようとする、相手(他者)とのつながりを重視する思想と言っていい。小倉寛太郎は、何よりも分かち合いを大事にする男だった。
その楽しみの共有の場が、サバンナクラブの例会である。これは上記の小倉さんの趣旨に沿って、隔月の第1土曜日に開催される。

もう少し詳しく述べると、予め決められたスピーカーがスライドやビデオの上映を交えながら、アフリカからの“里帰り報告”を行うのだが、これが実際にアフリカの風を受けるのと同じような楽しいひとときを作ってくれるのだ。また例会には、ケニア、タンザニア、ウガンダをはじめ、エチオピア、ボツワナなどの大使館からのゲストも出席する。そこでときどき飛び交うスワヒリ語が、その場の空気をアフリカに変えてくれるのである。
この例会には、小倉さんが定めた3つの「掟」がある。
一、スピーカーがマイクの前で話しているときには、私語をしない。
二、例会ではいつも同じ人としゃべっていないで、必ず一人以上、いままで話をしたことがない人と話す。
三、例会では商売の話をしない。どうしても話したい人は1分間1,000円、3分までとする。
3つの「掟」は例会の冒頭に必ず披露されるのが、サバンナクラブの伝統の一つになっている。「掟」を読めば、会員の一人ひとりの尊重と会員同士がつながることの価値が実にわかりやすく表現されていることがわかるだろう。このくだけた言葉遣いの人懐っこさもまた、小倉さんの個性の反映でもあるのだ。
例会と並行して重要なのは、隔月奇数月に発行する「サバンナ」という会報の発行である。
現在の会員約300名は全国中にいるので、この会報は会員同士をつなぐ絆として機能する。「リレーエッセイ」や「紀行文」、アフリカについての参考図書の紹介など、記事内容は豊富で、随所にレイアウトされる会員の撮影による写真がアフリカへの憧憬を誘う。
会員が撮影したこれらの写真は、サバンナクラブではとても大事な役割を担っている。
一つには、アマチュアであることを応募資格として、1人1枚の写真がプロの写真家の審査によって選ばれ、「サバンナの風」というカレンダーに掲載されるのだ。このカレンダーの収益は、東アフリカの人たちや動物保護のための一助として使われる。

もう一つは、毎年行われる会員の写真展「サバンナを訪ねて」への出展である。これはアフリカで撮影したものならどんなものでもよい。同じ動物の写真ばかりが重複しないように調整会議によって選定し、写真展では、さまざまな動物がいるサバンナの光景を会場に再現させてしまおうというのである。最近は池袋の東京芸術劇場でこの写真展を行っており、6日間で1,000名ほどの来場者がある。
そして、自分たちがサファリを楽しむだけでなく、それができることへの感謝を示すべく、東アフリカ諸地域への恩返しプロジェクトを行うことも、サバンナクラブの大切な取り組みだ。
例えば、密猟防止用の4WDパトカーを東アフリカの国立公園や保護区に寄贈したり、ケニアのカジャド地方(マサイ地域)の小学校の全面改築資金を援助したりと、さまざまな支援活動がある。さらに、ケニア・キテンゲラ地区にある託児所兼孤児院への敷地の買い足しや運営費などの支援を行い、タンザニアで密猟を取り締まるレンジャーの遺族へ生活資金を援助するという活動も行っている。
いずれも小倉さんが事務局長時代に始めたもの、または彼のアイデアが後年実を結んだものだ。
サバンナクラブは、東アフリカに魅力を感じる人なら、誰でも会員になる資格がある。私たちの活動に関心のある方は、以下のホームページを参照してほしい。
http://savannaclub.jp/index.html
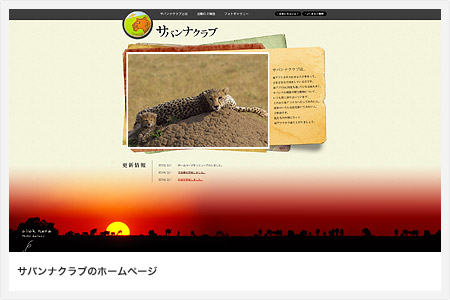
いささかサバンナクラブの広報宣伝のような書き方をしたが、これには理由がある。
平成14(2002)年に小倉さんが亡くなってから、何人かの人が事務局長の仕事を担ってくださったが、あるとき、サバンナクラブ古参会員の阿部昭三郎さんから次期事務局長就任の打診を受けた。しかし私は、設立時から参加されている他の長老会員の方々に比べたら、会員としてはまだ新参者(年齢こそ80歳だったが)だという気持ちがあったので、最初は断ろうと思っていた。
ただ、この頃は実務的な仕事からはリタイアした身だったので、阿部さんの熱意ある依頼を考えるだけの気持ちの余裕があった。
しばしの思案の末、小倉寛太郎というかけがえのない旧友の遺志をこの先も継続して形にしていくことは、私にとっても何か意味があることかもしれない、そういう考えに突き当たった。それともう一つ、好きな写真も何かに貢献できるかもしれないという思いも湧いてきたのだ。
そして平成20(2008)年6月、私はサバンナクラブの事務局長をお引き受けすることにしたのである。
つまり、この項の記述の仕方に、いささかサバンナクラブの広報宣伝めいた物言いが見られるのは、事務局長としての仕事の一貫だからである。ここは一つご了承願いたい。
このサバンナクラブ事務局長としての仕事は、これまで続いてきたサバンナクラブの全ての活動を事務方の長として支えることがメインである。
ただ、一つだけ私の経験上これは必要だと思って新たに実行したことがある。サバンナクラブを任意団体から一般社団法人として登記するということだ。
これは、かつて日本シニア・ゴルファース協会(以下協会とする)の税対策委員長・広報副委員長を引き受けていたとき、協会の預金(会長名義)を横取りしようとした反社会的な人物から協会組織を守るために、地位確認訴訟を起こし、示談に持ち込んだ経験が生かされている(平成14/2002年)。
その後、私が協会の専務理事になったとき、この裁判経験から学び、それまで任意団体(人格なき社団)だった協会を一般社団法人として登記した(平成23/2011年)。これによって名実ともに協会外部からの敵対的な介入を排除し、協会組織を法律的に守ることが可能になったのである。
サバンナクラブの一般社団法人としての登記は、この日本シニア・ゴルファース協会登記の前年(平成22/2010年)のことだ。どちらも私の楽しみを生み出してくれる“宝箱”のような大切な団体である。会員たちが余計なストレスのない状態で健全な活動をしていくためにも、法律の観点から2つの組織を守っていきたいと考えたのである。
サファリにある自己成長させる力
大迫力!「ヌーのイナヅマ渡り」
自分がそれまで親しんでこなかった世界と接点を持ち、その世界に何か新しい意味を見出し、そしてそれを自分のなかに受け入れようとするとき、人間は成長のチャンスをつかむような気がする。例えよい年齢になってからの経験でも、それは変わらない。
72歳で最初のサファリ体験をして以来、東アフリカの大平原で見てきたあらゆる出来事が、まさにそんな自己成長の源泉だった。自分の未熟さを知り、自分をもっと成長させようと思わせる力が、サファリにはある。
それまで自分ではそこそこ完成度を上げてきたと思い込んでいる経験や知識も、広大なサファリの風に吹かれ、そこに生きる動物たちの野生を目の当たりにすると、「ああ、オレはまだまだだったんだなぁ」と思わざるをえないのだ。
平成12(2000)年に小倉寛太郎さんにガイドされて出かけた初めてのケニアサファリを入れると、私は合計で4回のサファリを経験してきた。あとの3回は、平成14(2002)年の再度のケニアサファリ(小倉さん不在で寂しいサファリだったが)、平成18(2006)年と19(2007)年のタンザニアサファリである。
それぞれ濃密なサファリ体験を全て記すことはできないが、最も印象に残っていることを一つ紹介しよう。
タンザニアの西北にセレンゲティ国立公園という自然保護地域がある。面積で言うと14,637㎢、と言ってもピンと来ないかもしれないが、東京都と埼玉県、それに千葉県と神奈川県を合わせたほどの面積と言えば想像がつくだろうか。ライオンやチーター、カバ、シマウマ、ジャッカルなど、一般にアフリカを連想させるような多様な動物が約300万頭も生息している。
そのなかでもひときわ注目を集めるのは、何と言ってもヌーである。このセレンゲティにいる動物の3割以上、110万〜150万頭がヌーだと言うから、その群れ(マイグレーション)の壮観さも想像できると思う。世界最大の野生動物の集団というわけだ。
ただ、私がこのヌーの群れに遭遇したのは、そのセレンゲティのさらに東にあるンドゥトゥ湖においてだった。
セレンゲティや隣のケニアのマサイマラなどから豊富な草を求めてヌーの群れがやってくるのが2月から3月にかけての小雨季。メスがオスのグループと分かれて、出産を行う季節だ。
そして春になると、オスとメスの集団は再び合流し、子育てをしながらの大移動が始まる。メスは一生懸命に草を食べ、子どもにミルクを与えなければならない。目の前の草を食べ尽くし、さらなる草を求めれば、必然的に移動せざるをえないのだ。
このとき、シマウマなどの草食動物も一緒に移動することになるが、その大移動に引き寄せられるように、ライオン、ヒョウ、チータ、ハイエナなどの肉食動物も集まってくる。主に草食動物の子どもを狙うためである。
私たちがンドゥトゥ湖付近に出かけたのは2月〜3月。ちょうどその年に生まれた子どもたちを引き連れて、餌となる草を求めて大移動を始める季節だ。
ンドゥトゥ湖はンゴロンゴロ自然保護区の西南に位置する、川のように細長い湖。ヌーの大群がその細長いンドゥトゥ湖に近づきつつあるところに私たちは出くわした。ヌーほどの数はいないが、シマウマの群れも並行してやってくる。
このとき同行してくれた阿部さんは、サファリ歴40年以上のベテランである。彼は私とは別の車に乗り、お互いに無線で連絡を取り合いながら、ヌーをカメラに収めるベストロケーションを探しつつあった。このときは阿部さんから、「そろそろ湖に入りそうだ」と連絡があり、大急ぎで湖畔に急行した。
私たちは期待しながら、ヌーの大群の行末を注視していたのだが、大きなうねりを伴ったヌーの動きに妙な緊張感が漂っているように思えてきた。
通常なら岸辺に沿って湖の反対側まで遠回りするところだろうが、このときのヌーの動きは違った。オスのライオンが1匹、湖の端の高台にメスのライオンが20mほどの間隔で一直線に並び、ヌーの大群に目を光らせていたのだ。ヌーたちの緊張の理由はそれである。
当然ヌーたちは、湖畔を進むことができなくなったとき、ついに湖を中央突破せざるをえなくなるのだ。
どうするのだろうと思って見守っていると、次の瞬間、先頭のヌーが意を決して湖に飛び込んだ。ヌーでもシマウマでもゾウでも、先頭を行くリーダーはメスである。そのメスのヌーが飛び込むと、その後に続いて次々と群れの一団が湖に入っていく。これがものすごい勢いなのだ。水はそれほど深くないが、大群が動くと水煙が立つ。
そのまま行くかと思ってカメラを構えていると、不思議なことが起こった。先頭のヌーがまだ50mも進んでいないのに、急に反転し、元の岸に戻ってくるではないか。
何が起こったのかと周りを見回してみると、何と、ヌーが渡ろうとしていたその対岸に、1台の自動車が待ち構えているのだ。
「何をやっているんだ、あんなところで!」と憤慨しながらカメラの望遠レンズで覗いてみる。すると、一人の欧米人のお婆さんが、ヌーの行く手を阻むかのような場所で、悠長にも双眼鏡を覗いているではないか。「対岸でヌーを待つなんて、愚の骨頂だな」と吐き捨てるように言う阿部さん。
リーダーが引き返してしまったら、群れもそうするしかない。一度離れた湖岸に、群れがかたまりになって膨れ上がっていくのが見えた。大半のヌーが叫び声を上げ、混乱しているのが伝わってくる。
「伊室さん、これはヌーたちが落ち着くまで待つしかありませんよ。しばらくはパニック状態でしょうから」
人間による些細な介入でも、動物たちにはとんでもない動揺を生じさせてしまうのだ。対岸に陣取っていたお婆さんの罪は重い。
仕方がない。私たちは車の後部座席で待機することにした。
だが、しばらくすると運転手が叫んだ。「Gnu moved! Gnu moved!」。
私たちはあわてて立ち上がり、ヌーの大群に向き直った。そして、そのとんでもない光景に、私は思わず声を上げてしまった。
先頭のヌーは既に先ほど引き返した湖の地点まで進んでおり、それに続く群れたちの勢いがどんどん増していく。私は夢中でシャッターボタンを押し続けた。

ヌーは巨大な群れをなして湖水を蹴散らしながら懸命に前進していく。そして、子どものヌーが遅れまいと親のあとを必至についていく。その光景が何とも言えず健気だ。私の心は大きく動かされていた。
その間、ほんの一瞬だけファインダーから目をずらし、対岸を見てみると、あのお婆さんも自動車も消えていた。簡単な話だ。ヌーたちが改めて湖を渡り始めたのは、彼らの行く手を阻むものが存在しなくなっていたからである。
再びファインダー越しにヌーを見ながらシャッターを切っていると、私はまた声を上げてしまった。ヌーの群れ全体が、まっすぐ行くのではなく、ジグザグに大きくうねりながら進んでいくではないか。詳しくはわからないが、少しでも危険の少ないルートを本能的に選んで進んでいるようにも見える。
「すごいねー、伊室さん。こんなのは僕も見たことがないよ。まるで“イナズマ”のようだね」
阿部さんがそう言ったので、私たちはこのヌーの迫力ある湖の横断を「ヌーのイナズマ渡り」と名づけることにした。40日間のンドゥトゥ滞在中、ヌーが湖の中央突破を試みたのは2回だけだった。

*このときのヌーの大移動の写真は、以下のURLから。
https://www.flickr.com/photos/111442294@N05/sets/72157641437044704/
野生動物の世界に存在する「節度」
サファリを知る、自分を知る
この「ヌーのイナズマ渡り」はこれまでのサファリでは格別の体験だった。もちろんこれ以外にも、壮大な東アフリカの原野の至るところで、そこでなければ見聞きできない貴重な出来事に遭遇することが多々ある。どれもが目を見張るものであることは確かだが、一方で、動物たちからのメッセージ性が含まれているのではないかと思わせるような出来事にも遭遇する。それは、私たち人間のあり様に反省を促すようなメッセージだ。
例えば、平成12(2000)年に小倉寛太郎さんと初めて出かけた、ナクル湖国立公園でのサファリでのこと。ライオンが2頭のバッファローを倒した直後の現場に遭遇したのだ。
ハンティングの瞬間は見逃したが、数頭のメスライオンが獲物の至近距離にたむろし、その周りに子どものライオンがやはり数頭、早く食べたいとばかりに舌なめずりをしてうずくまっていた。何をしているのかと言えば、この家族の主であるオスライオンを待っているのである。
私たちは40mほどのところ(もちろん自動車の中だ)からその様子を伺っていた。すると、森の方からオスライオンがおもむろに登場し、御馳走様と言わんばかりに大きな肉のかたまりを咥え、再び森のなかへと戻っていった。その直後、待ちかねていた子どもがまず獲物に喰らいつき、さらに待っているメスたちがようやく獲物に群がる。
面白いことに、獲物を食べているライオンがその気になればすぐに捕まえられそうな距離(20mぐらいだろうか)のところで、バッファローの群れが悠然と歩いているのだ。なかには、平気な顔をして草を食んでいるものもいた。
ライオンはフレッシュな肉しか食べない。2頭のバッファローなら、当面は1家族がお腹いっぱい食べるには充分な量だろう。だから、少なくとも空腹になるまでは、それ以上バッファローを襲うことはない(つまりこれ以上の余計な狩りはしない)。
一方バッファローの側は、満腹しているライオンにはしばらくの間は襲われることはないとわかっている。仲間は犠牲になったが、その犠牲によって束の間であっても自分たちに平和な時間が保証されることを知っているのだ。
私はここに、野生動物の世界に存在する「節度」というものを感じる。人間なら、自分の欲望を満たすために、際限なく狩りを繰り返すのではないだろうか。

事実、人間には単に食べるという行為だけでなく、勇ましい狩りの姿を記録に残して名声を得たり、あるいは野生動物の剥製を作って富の象徴のようにディスプレイしたりという時代があった。それらは全て人間が抱えるさまざまな欲望の反映であり、その欲望には際限がない。その挙句に、文字通り「節度」を失った今日の人間世界の姿があるのかもしれないのだ。
また、東アフリカに限らず、地球上の野生動物全体の種の多様性や個体数が減少しているという事実がある。例えばライオンも絶滅危惧種に準ずる“危急種”であり、1950年代には10万〜40万頭いたと推定されたものが、2004年段階では多めに見積もっても5万頭を下回り、少なく見積もれば1万6000頭程度と推計されているのだ。
これは野生動物の世界だけの問題ではなく、人間が自然とのつき合い方のバランスを崩し、その結果として野生動物の世界が犠牲になっているという現象だ。その意味では、人間は野生動物全体への加害者と化している。これも「節度」を失っている人間の側の問題だと言える。
もう一つ、私の記憶に強く残るサバンナでの光景がある。初回のタンザニアサファリでのことだ。
セレンゲティ国立公園の草原で車を走らせていると、何羽ものハゲワシや大型の鳥が1頭のシマウマの死骸に群がっているところに出くわした。シマウマが誰によって倒されたのかはわからないが、おそらくはライオンが倒したものをハゲワシどもが先を争って啄んでいるのだ。
最初にシマウマの横腹を引き裂くのはミミヒダハゲワシである。これは最も獰猛だとされるハゲワシの種類で、翼開長は最大で2.9mもあり、他のハゲワシと比べると明らかに一回り大きい。
このミミヒダハゲワシが一番先にシマウマの生肉を食べられるのは、一番大きくて強いという理由だけではない。鋭く大きな嘴の先が鈎状に曲がっているため、横腹を引き裂くことができる。逆に言えば、鳥のなかで最初に獲物の肉にありつけるように、体長が大きくなり、力も強く、嘴も曲がるという進化を遂げたとも考えられる。

ときどき、セジロハゲワシやシロガシラハゲワシといった力では負けるハゲワシたちが、ミミヒダハゲワシのスキを狙ってシマウマの死骸に上からのしかかろうとするが、そんな勝手な振る舞いを許さないミミヒダハゲワシとの間でちょっとした乱闘騒ぎになる。しかし、所詮は力の弱いハゲワシ連は追いやられてしまう(サファリを楽しむ人間にとってこの騒ぎはなかなかの見ものだ)。
こうした多少の混乱はあるものの、結局、力の弱いハゲワシたちはミミヒダハゲワシが食べ終わるまでその周りに群がり、肉にありつけるまで順番を待たなければならないハメになる。そしてそのさらに外側には、より力の弱い何種類かの鳥たちが順番待ちをしているのである。
よく見ると、弱いハゲワシたちの嘴はミミヒダハゲワシようには鋭く曲がってはおらず、厚みもない。その外側で待つ鳥たちの嘴がもっと小さく、ひ弱に見える。そんな嘴では、最初にシマウマの肉に食らいつくことはむずかしい。
つまり、ミミヒダハゲワシがまっ先にその鋭く曲がった嘴で横腹を裂くことは、結果として、他のハゲワシや鳥たちの嘴でも食べやすい肉へと加工してやっているに等しい。ミミヒダハゲワシに肉の優先権が与えられているのはそのためでもある。
肉にありつく優先順位とそれぞれの種の形態進化には相関性がある。そしてそこに、それぞれの種が生存していくための分業関係が成立しているのである。
私は、このシマウマの肉を巡るハゲワシと鳥たちの分業のなかにも、自然と調和して生きる野生動物の「節度」を見る思いがする。
人類の先祖とされるヒト(ヒト亜属)が誕生してから約700万年という時間が経っていると言われるが、私がサファリで遭遇した野生動物たちは、その人類誕生のずっと以前からいまと似たような自然のなかで調和し合いながら生きてきている。ところが新参者の人類は、より賢く進化したはずなのに(いや、賢くなりすぎたせいなのか)、欲望ばかりを膨らませて、自然動物たちが持っている「節度」をどこかに捨て去ってしまったように思えるのだ。
このような人類や文明への批評・批判は、ある意味では今日的にはよく耳にするものかもしれない。しかし、東アフリカのサファリに足を踏み入れると、それまで頭のなかだけで「そうに違いない」と考えてきたことが、「本当にそうだ!」と、身体レベルでの実感に置き換えられてしまうのだ。脳の中身がすっかり入れ替えられてしまうと言っても大げさではない。
大自然のなかで繰り広げられるヌーやライオンやハゲワシたちの野生の行動を目と鼻の先で体験すると、まずは最初、とても言葉にはなりがたい体感的なものが体中に湧いてくる。この体感的な感覚こそ、サファリ体験の最大の効能だと思う。
この体感の次に、「人間とは何とバカバカしい存在か」と思えるようになり、さらに「節度」や「調和」とかいうような奥深い言葉が心の底から湧いてくるとき、サファリ体験による大自然の価値と意味のシャワーが存分に降り注がれていることを実感するのだ。
私がもっと若い頃にサファリを知っていたら、その魅力により深く取り憑かれてしまっただろう。あとどれくらい行けるかはわからないが、自分の魂を裸にして、その芯の部分に何があるかを知るためにも、サファリにはまだまだ足を運びたいと思っている。
サファリを知ることは、まさにサファリを通して自分を知ることなのである。
デジタル一眼レフに切り替えた日
写真は私の“生涯の友”となった
サファリが与えてくれるこのような体感は、人間には太刀打ちできない“本物の自然”の力によってこそ生み出されるものだ。普段、人工物ばかりの都市に住んでいる人間には、とりわけこの体感的な世界は驚くべき圧力として感じられるのではないだろうか。
しかし最近は、さまざまな事情から、10数人単位のツァーで行われる観光サファリという商品が仕立てられるケースも増えた。これは現地の地域経済を少しでも回していくためには、ある程度は仕方のない面もある。しかし、これでは私の言うサファリの“本物性”が薄められてしまうように思う。
やはり本物のサファリは、現地ガイドの情報やノウハウを尊重しつつ学び、彼らとのコミュニケーションをしっかりと図りながら、できるだけ自分たちの判断で動物を探そうとすることから生まれてくるものだ。もちろん最初からできることではない。率直に言えば、サファリを本当に楽しむためには、どうしてもある程度の経験の積み重ねが必要だろう。
しかし、その経験を重ねるたびに、サファリに対する“味覚”はジワジワとその醍醐味を捉えるべく発達していくのだ。
ときとして忍耐と寛容が試され、その挙句にようやく自分たちの感覚で動物との出会いの状況を創り出せたとき、その喜びは倍増するといっていい。その視点から言えば、サファリはまことに創造的な行いなのである。
サファリで体験した出来事や光景だけを一つひとつ言葉で描写することは可能だが、そのときの感覚や体感までをそのまま相手に伝えることはなかなかむずかしいものだ。それがまさに体感である所以である。
そうなると、言葉よりも画像や映像の方がずっと訴求力を発揮する。私がサファリの自然や動物の撮影に夢中になってしまうのは、私のサファリでの体感を写真に込めたいと思っているせいなのかもしれない。写真は私の言葉でもある。
ただ、アフリカというロケーションで写真という仕組みを自分の思い通りに使いこなすためには、意外に厄介なことにぶつかることもある。ときどき、相手がモノであり機械であることを思い知らされるのだ。
2000年に小倉寛太郎さんと最初にケニアサファリに行ったとき、こういう会話があった。
「小倉さん、写真のフィルムですけど、何本ぐらい持っていったらいいでしょうか」
「そうですねぇ、1日あたり何本ぐらい撮ると決めて、それに予定日数をかけその倍のフィルムを持っていくといいでしょう」
このときのサファリは15日を予定していた。初めてこのことなので、1日あたり最低でも12本(36枚撮り)は撮影したいと欲張ってみたが、そうなると合計で360本になってしまう。これにはさすがに自分でも呆れた。ものすごい量の荷物になってしまうからだ。いくらか迷ったが、結果としては、何とかこの360本のフィルムは持っていくことにしたのだ。初心者の気負いかもしれない。
ところがもう一つ、フィルムを持って行くについては問題があった。機内持ち込み用荷物のX線検査でフィルムが軽微ながら露出してしまうのだ。1回のX線荷物検査ならあまり問題はないが、成田、乗り換えのドバイ、そしてナイロビの3か所で露出すると、フィルム感度はかなり劣化してしまう。撮影してからの帰国途上に、再びこの3か所を通ることになれば、合計で6回もX線に曝されることになり、映像にかげりが出ることがある。
ただ、最初のケニアサファリでは、結果として200本ほど残ってしまったので、次の2002年のサファリまでナイロビの小倉さんの知人宅の冷蔵庫でその200本は預かってもらうことにした。
しかし今後のことを考えると、既に一般化していたデジタル一眼レフを使う方が圧倒的に有利だと考え、2002年のサファリでは結局キャノンのEOS-ID(平生12/2001年12月発売)を持っていくことにした。1枚のCFカードに大量の写真データを保存できるから、荷物もずいぶん減らせる。
ただ、長年ライカM6を使っていた個人的な経験からすると、このデジタル一眼は画素数がまだ少なく、フィルムの解像度には叶わないという印象を持った。そこで、2007年の3月にタンザニアサファリのときには、上位機種のEOS-IDsMARKⅡ(平成16/2004年11月発売)も購入し、EOS-IDとともに2台のカメラを持っていくことにしたのだ。
もちろん大量のフィルムを持っていかずに済むという利点も重要だが、画素数が格段に上がって解像度がよくなったことが最大のメリットだった。このカメラのおかげで、私のサファリにおける被写体ハンティングの意欲はますます向上することになったのである。
ちなみに、私は平成20(2008)年の傘寿(つまり80歳)の記念に、これまでのサファリ体験で撮り貯めてきた写真を整理し、写真集にまとめた。これに「サバンナの輝き」(Splendor of the savanna)とタイトルをつけたのは、自然のなかに生きる動物たちの生命力に文字通りの“輝き”を見出したからにほかならない。

*サファリの写真は、以下のURLから。
https://www.flickr.com/photos/111442294@N05/sets
ところで、私は“新しもの好き”だろうか? どうやらそうらしい。
カメラを買うのも、自動車を購入するのも、あるいはゴルフにのめり込むのも、そのスタートはどれも若いときだった。あるいは適度に歳をとってからも、同年輩では比較的早くパソコンやタブレット端末に慣れ親しんだ方ではないかと思う。
そのときどきに、私の好奇心を刺激し、私に活力を与えてくれそうなものには何らかの直感が働いてすぐに飛びつく傾向があるようだ。たまたまそれらは、私にとっても世の中においても“新しいもの”であったというだけのことにすぎない。
ただ言えることは、それぞれのアイテムが、機能的にも精神的にも、私の生活に潤いを与えてくれているということだ。しかも、それらの“新しいもの”を使いこなしていくうちに、私は自分の趣味的な世界を創り上げることはもちろん、さまざまな人たちとつながることができた。ゴルフ然り、写真然りである。
とりわけ写真は、いろいろな場面で私に役割を与えてくれた。サバンナクラブのような新しい出会いをより豊かな関係に育ててくれたのも写真を通してだったし、陸軍幼年学校の同期や大先輩といった古くからのつながりをより強固なものにしてくれたのも、長年、親しんできた写真というアイテムのなせる業だった。
その意味において、写真は私の表現媒体であると同時に、さまざまま出会いをつないでくれる人間関係の媒体でもある。
この私のサイトに「PHOTO BOOK」というページを設け、さらに多くの写真を他のサイトにアップロードしたのも、私の写真に対する思いの一端に触れてほしかったからだ。写真が私のいた空間を切り取るとともに、私の生きた時間の切片にもなっていることがおわかりいただけるだろう。
http://kazuyoshiimuro.jp/gallery/
写真はまさに私の“生涯の友”となったのである。
経験した2つの病気
完治への推進力はサファリへの希求
そんな“新しもの好き”の私が古くから最も長くつき合っている相手は何者か? それは、私の身体である。
この身体というものは、自分のもののようで自分ではないことがある。なかなか自分の言う通りに動いてくれない場合がそれだ。年齢を重ねてくれば、日常的にも身体の好調・不調の波は如実にある。ただ、自分で自分の身体がコントロールしづらいと最も顕著に感じられるのは病気のときだ。
どちらかと言えば社会に出てからも痩身を維持してきたし、中年以後もメタボ症候群に仲間入りすることもなかったので、健康状態を問われれば「概ね良好」と答えるのが常だった。しかし振り返ってみると、20代半ばに結核、50代後半に一過性の脳虚血症と急性肝障害と、入院を必要とする病気はそこそこ人並みに経験している。
結核に関しては、幸いにして戦後に日本でも保険適用になった抗生物質で完治できた(第2章 第1部参照)。このとき見捨てないで見舞いに来てくれた女性と結婚できたのだから、病気の経験は必ずしも否定的なものばかりを呼び込むものではないと思ったものだ。
他の2つの病気は、ともに安田火災の常務取締役時代の超多忙ななかでの過労が遠因だということがはっきりしていたので、適切な治療と適度な療養が元通りの身体にもどしてくれた。それに、このときには『よどばし通信』のネタ探しをしたり編集をしたりして、退屈なはずの入院生活を充実させてしまったこともあり、病気になる前の仕事に対する精神的な“力み”も取れて、むしろ病気の経験を通してそれまでの自分を顧みるよい機会が与えられたほどだ。
いずれにせよ、病気そのものが持つ否定的なイメージとは裏腹に、療養中の時間をただ空白のままにすることなく、あるいはまた「治ったら何をしようか?」という前向きな思考をセットすることによって、“転んでもただでは起きない自分”を創ることができたわけだ。
そんな私が、76歳のとき(平成16/2004年9月)前立腺ガンの宣告を受けた。
その2年前、私は学生時代からの旧友でありサファリの師匠でもある、小倉寛太郎さんを肺ガンで失っていたし、幼年学校の同期も含め、何人かの友人をガンで亡くしていた。その意味では、それなりの歳でガンを発症したとなると、全く心配がなかったと言えばウソになる。
ただ、これまでの病気経験もあって、私は比較的冷静に自分の病気のメカニズムについて知る癖がついている。どういう原因で、どういう経過をたどって発症にいたるのか、さらには、どのような治療法があり、その治療法がどの程度効果的であるのか、その根拠は何か? などなど…。私はかなりしつこく医師に聞くことにしているし、場合によっては自分で詳細を調べてみる。
自分の病気について知らないままでは、病気が治そうとする自分の意志にまで侵食してしまうような気がするからだ。
幸い、私を担当してくれた医師は、私のガンについてあらゆる角度からしっかりと情報提供してくれる方々だったので、私は自分の病気について理解を深めながら治療に向き合うことができた。その結果、いまもこうしてぴんぴん生きているところからすれば、このガン治療が成功したことはおわかりいただけるだろう。
実はこのガン宣告から完治に至るまでのことを、平成19(2007)年1月の東松山CCの会報に書いたことがある。「経験者は語る 前立腺がん」と題したリポート風のエッセイだ。
このエッセイをお読みいただくとわかるが、医師や本などから得たガンのメカニズムや治療法についての情報を淡々と書いている。実際に発症してから、自分で自分のガンについて多くのことを知りたいと望んでいたのであり、そのような知識への好奇心がガン治療を前向きに進める活力になっていたことも確かだ。
しかし、このときの私のガン治療を完治に向かわせた大きな推進力の一つは、やはり当時夢中になり始めていたサファリへの強い希求だったと言っていい。
そのリポートの冒頭部分にこうある。
「…もしガンになっていたらアフリカへは行けないだろうし、私の場合、ガンの発見が少し遅れて他の臓器に転移していたら、今頃こんなことを書くことは許されなかっただろう…」(表記はママ)
一見さらっと書いているが、それは私の性格のせいであって、いま考えれば本音の部分を正直には表に出していない。ここで自分のガン治療の情報をゴルフの仲間に発信しているその潜在意識には、「これからもみなさんとのつながりを大切にしていきたい」というメッセージが潜んでいたのではないかと振り返ることができる。
もちろん私にとっては、ずっと“第二の伴侶”として楽しんできたゴルフの重要度も高い。この頃の私は、株式会社東松山カントリークラブの社長を引退した直後であり、日本シニア・ゴルファース協会の総務委員長を務めていたせいもあって、古くからのゴルフ友だちには恵まれていた。それはもちろん、私の日々の生活において、楽しく、愉快なことだった。
しかし、サバンナクラブでの新しい出会いはその後の私の人生にとって何ものにも替えがたいものになっていた。それは、期せずして同じような病気で先に亡くなってしまった畏友、小倉寛太郎がつないでくれた大切な仲間の集うところでもあるからだ。
私がガンを治そうとする強い意志を持てたのは、再び東アフリカのサファリにしっかりと立ち、その野生に生きるライオンの親子やヌーの群れにカメラのフォーカスを合わせたいという強い思いが深層にあったせいでもある。過去2回のサファリ体験の強烈なイメージが、私の身体レベルにしっかりと刻まれていたのだ。サファリの記憶が、私が古くからつき合ってきた身体に、まさに新たな生の息吹を与えてくれたのである。

そして主治医から「アフリカOK」のお墨付きを得たその3か月後、平成18(2006)年2月、古参会員阿部さんのお誘いを受け、私は早速タンザニアサファリに出かけていった。
私の身体について、もう一つつけ加えておこう。
平成22(2010)年の7月、私は地下鉄東銀座駅の階段付近でうまく呼吸ができず、思わず足が止まってしまった。それでも手すりにつかまって何とか階段を登り切ったのだが、息苦しさは変わらない。
整形外科医の私の息子に連絡し、彼の母校の同級生である呼吸器科の医師を紹介してくれるように頼んだところ、呼吸器科には同級生はおらず、救急室にいる友人からその症状は心不全だと告げられ、翌日の朝、タクシーを飛ばし、J医大病院の救急室に飛び込んだ。
さまざまな検査をしてみると、何と脈拍が30で、健康の人のほぼ半分しかない。これが要因で血液が身体のすみずみには行きわたっていなかったため、実はすでに各臓器の不全が始まっていたのだ。心不全の一歩手前だったのである。早速、そのまま循環器集中治療室に運ばれ、応急処置が施された。
手術とは言え、局部麻酔のためぼんやりした意識のなかで、なんとなく話し声だけが聞こえてくる。
顎の下の静脈から40㎝ほどの針金を心臓まで通し、これに電気を通して脈拍を上げる手術らしい。脈拍数が60にセットされた処置で血液の循環がよくなっていく。すると猛烈な尿意が起こってきた。体内に溜まりに溜まった余分な水分が膀胱に送り込まれたのだ。尿が何と1時間に900CCも出た。
そこに担当医の声が聞こえてきたのだ。「あぁ、よかった!」。
どうやら、各臓器が改善の方向に向かったらしい。
病名は「房室ブロック」。心臓の結節からの信号を房室が受け取ることによって心臓の筋肉が動く仕組みになっているのだが、この信号伝達のメカニズムに何らかの理由で支障を来すことによって起こる病気だ。
「原因は?」と私が聞けば、「加齢ですね」と担当医。82歳の私は納得せざるをえなかった。
1週間後、体調が整った頃合いを見計らって、ペースメーカーを植え込む手術を受けた。鎖骨の下にポケットをつくり、そこに直径5㎝ほどの円形の機械を挿入するのである。
ペースメーカーを使って心臓を駆動させている人は身体障害者1種1級となり、東京都から障害者手帳が配布される。このとき、歳を取ることは少しずつ障害者になっていくことだと実感した。齢を重ね、すんでのところで死にそうになるほどの病気をして、ようやく世の中の障害者に向けるべき目が開かれたのである。
つき合いの古い身体も、うまく使いこなしていかないと、いつまた反乱を起こさないとも限らない。しかし、丁寧に使っていけば、まだいくらかは言うことを聞いてくれそうだ。

東幼での良質な人間教育を伝えたい
1年半かけた『再販 東幼外史』編集
最後に、古い事柄を新たに経験し直すということについてもう一つ話そう。
平成21(2009)年のことだが、私は東京陸軍幼年学校(以下東幼)46期生代表幹事を引き受けることになった。このとき、私がやらなければならないと思ったのは、かつて制作された『東幼外史』という冊子を再編集することだった。
この『東幼外史』は、昭和43(1968)年に東幼の46〜48期の3期が合同で東幼会(東幼の同窓会)の幹事期を担ったとき作った冊子だ。内容は、東幼に学んだ歴代期生の生徒の手記をまとめたもの。各期生代表が個人的な視点から東幼の思い出を記した文章の集成である。編集責任者は、東幼時代の親友の一人、本田尚士君だ。
その「あとがき」に本田君は述べている。
「…将来必ず更に客観的な資料と、多数の記憶による想い出を加えて東京陸軍幼年学校正史を残したい…」(表記はママ)
本田君のこの思いは、昭和57(1982)年に刊行された公式の学校史、『わが武寮─東京陸軍幼年学校史』のなかに結実されることになった。『わが武寮』のなかの一つの章(第5章)「わが期を語る」に、『東幼外史』の中身がそのまま収められたのである。

だが、『東幼外史』が産声を上げた昭和43年は、私たち46期生もまだ40歳になるかならないかの頃だ。私が東幼46期の代表幹事になったのは、それから41年後。既に倍の年齢になっていた。そのうえ、『東幼外史』は全ての期生の文章が出そろっていたわけではなかった。初版で執筆されていない期の先輩や後輩たちもすでに80代前後だ。ここで原稿を依頼しなければ、全ての期の手記がそろうチャンスを逸してしまう可能性もある。
私はこのことに危機感を持ったのである。
以前にも書いたが(第1章 第1部)、私たちが体験した陸軍幼年学校(陸幼)の教育は、日本陸軍の内務班を象徴するような「鉄拳制裁」のイメージとはほど遠いものだった。14歳の少年期から将来の陸軍将校を養成するための初等教育の場である以上、自分を律する厳しさは重視されていたことは確かだ。しかしそれは、生徒の人格を尊重する教員と生徒との間の信頼関係の上に、自立的に築かれていくものという前提があった。むしろ暴力は禁じられていたほどだ。
少なくとも、私たちが東幼で直接教えを受けた湯野川龍郎校長(当時大佐、最終階級は少将)に関して言えば、生徒の内発的・自立的なやる気を何よりも後押ししてくれた、尊敬すべき教育者だったと確信する。凡庸な教官が唱えるお為ごかしの精神論を嫌い、「生徒ができないのは生徒が悪いのではない。教える方の教え方が悪い」と教官たちを叱咤するような人だったのだ。
しかし、陸幼で生徒の自発性を喚起するような丁寧な敎育を受けながら、予科士官学校、士官学校、場合によっては陸軍大学校を経て任官されるようなエリート将校たちが、当時の軍閥における権力闘争にまみれてしまうこともあった。その状況下で、比較的まっすぐに幼年学校時代の教育を受容した将校は、どちらかと言えば当時の陸軍上層部からは白い目で見られる存在になっていくケースが少なくない。
私が直にお会いした前述の後藤四郎さん(熊本幼年学校26期、士官学校41期)をはじめとして、多くの大先輩たちのなかには、皇道派と統制派の権力闘争に巻き込まれ、特に二・二六事件後に皇道派が一掃される状況下では、過酷な戦地へ左遷されたり(山下奉文大将など)、あるいは予備役に編入されたり(小畑敏四郎中将など)している。
少年期にせっかく丁寧で上質な人間教育を受けて巣立ち、将校に任官されていっても、陸軍上層部内にある無倫理的な排除性や加罰性の色濃い軍閥文化に染まっていけば、世情に長け、汚れた大人の分別を使って表面的にうまく立ちまわる軍人ができあがってしまう。戦時下の陸軍上層部に地位を獲得していった将校には、そういった人材が少なからずいた。
そう考えると、幼年学校と予科士官学校までで敗戦を迎えた私たちの年代の同期は、綿密な戦争シミュレーションによって負けるとわかっていながらアメリカとの戦争に無謀にも突き進んだ、陸軍上層部の汚れた空気に染まらないまま、戦前の軍学校教育のよいところだけを記憶に刻み込んでいるのかもしれない。私のなかでは、悪評高いかつての軍閥政治のあり様と、上質な人間教育を授けてくれた陸軍幼年学校のあり様を一緒にしてほしくないという思いがあるのだ。
戦前の陸軍幼年学校でどのような教育が行われていたか、それは、特定の軍閥が支配した戦時下における陸軍の閉鎖的かつ陰湿なあり様と何が違うのか。私はそのリアリティを、かつて本田君が編集した『東幼外史』に投稿された真摯な文章のなかに見る思いがしていた。

そのような思いを持つ私への46期生代表幹事の話である。
初版発行からすでに40年を経ていた『東幼外史』のなかで、各期の同窓生たちによっていきいきと語られている陸軍幼年学校の姿を、世の中に広く伝えていく必要を感じたのだ。その教育内容やその雰囲気、教官や生徒たちの温かくも厳しく向き合っていた関係といったものは、ほとんど知られていないからである。
この再編集の作業は、抜けている期の諸先輩や後輩に原稿をお願いし、他の期で文集などを出している場合にはそこからの転載許可を得るなどして、文章は何とか全ての期を網羅することから始めた。カットは絵心のある2人の同期、I君とT君に依頼し、さらに48期のH君とO君に編集の助っ人をお願いした。
その甲斐あって、完成は奇しくも平成22(2010)年8月15日。タイトルは体をそのまま表す意味を込めて、『再販 東幼外史』とした。発行は東幼第46・48期生会である。
汗をかきかき、しかし愉快な仲間たちと分かち合えた、価値ある1年半の作業が終わった。
出会った全ての人たちが私の全て
「いつか、また、どこかで」
私は故郷の伊賀上野を離れて生活してきた人間である。そのスタートは、昭和17(1942)年4月、14歳のときの東京陸軍幼年学校(東幼)への入学だった。
この文章を最初からお読みいただいた方にはおわかりだろうが、その東幼へ入るきっかけとなったのは、中学でともに柔道に励んで汗を流した親友、宮本哲也君の一言である。
「飛行機乗りにならないか? 将校の飛行機乗りになるなら、陸軍幼年学校にいけばなれる」
そう言った宮本君は、一緒に受験した幼年学校には残念ながら不合格になり、名古屋の八高を経て京都大学に進学したが、若くして急逝してしまった(第1章 第1部)。
しかし、私の人生の大きな転機を作ってくれた宮本君のことは、いまでも思い出す。それは、生まれ育った故郷での友であるからだと思う。故郷は、場所の思い出だけでなく、人の思い出とともにあるものなのだ。
そして私は、名古屋の高名な易者、町井如水先生に「寿命は73歳!」「弾丸は外れる!」と言われたことを思い出す(第1章 第1部)。
陸幼の受験に合格するかどうかを聞きたいと思って父と一緒に伺ったのに、戦争で弾丸に当って死ぬことはないというところまではよかったが、生涯年齢まで決定されるとは思わなかった。もちろん「東幼には合格!」と答えてくださったときにはうれしかった。これは本当である。
確かに東幼には入学できたし、鉄砲の弾丸には当たらなかった。ということは先生の八卦の当たる確率は3分の2ということになる。
いまの私の本音を言えば、易学を信じるも信じないも、実はどちらでもないのだが、3つのうち2つが当っているということを考えると、先生は易者として優秀な方だったのかもしれない。
宮本君との出会いは、その後の私の人生からすれば必然的な意味を感じ、町井先生には他人の人生に影響する偶然というものがあるという面白さを感じる。そう言っては町井先生に失礼だろうか。
実際、必然にせよ偶然にせよ、彼らに出会うことがなければ、私は東幼に行くということもなければ、いまこうしてこの文章を書くことすらもなかったかもしれないのだ。
しかし平成27(2015)年3月現在、その町井先生のご高説による私の寿命も、もはや13年ほどもオーバーしてしまった。
73歳のときの私と言えば、ちょうど東松山カントリークラブの2度目の社長業を終わろうとしていた頃だ(平成13/2001年)。もしその当時に物故していたら、その後のケニアサファリ(2度目の)やタンザニアサファリでの楽しみもなく、フィルムカメラからデジタル一眼レフに切り替えることもなく、さらには、同期とともにやり遂げた『再販 東幼外史』の編集作業もないことになる。
もっとも、町井先生の言う通りに73歳で逝ってしまっていれば、その後に発症した前立腺ガンにも房室ブロックにもならないことにもなるから、病の苦痛は感じなかったことにはなる。しかし、病気になることによって学んだこともずいぶん多いので、どちらがよかったのかについては、簡単には判断しがたいように思う。
身内のことはあまり書いてこなかったが、例えば私が73歳で鬼籍に入っていたら、私の顔を知らないままに育つ孫もいることになるし、保険代理店の経営に勤しむ次男の仕事に感心することもなく、医師である長男に旧友の病気について相談することもないということになる。
あるいはまた、73歳で逝くということは、いまも元気にしている妻の登美子を一人残してあの世に逝ってしまうことを意味するのだから、そうなったら可愛そうだし、心配にもなる。もっとも、私の葬儀の日に、「おじいちゃんにはもっと長生きしてほしかったね」と子どもや孫に言いながら涙を流してくれるかどうか、一番心配なのはその点なのだが…(笑)。

何度か書いてきたことだが、人の人生は結局、出会いによってこそ成立しているとほぼ断定できる。いま記した73歳で亡くなっていたらという仮定の話をしてみても、その後の人生のステージでどれくらいの人間と出会い、私という存在を形づくってくれたかと自問してみれば、おそらく数えることなど不可能に近い。
まして、それ以前の私の人生を振り返ると、出会った全ての人たちが私という一個人の人生を形づくり、生かしてくれたのだとしか言いようがないのだ。
要は、私という人間は単に個人ではなく、出会った人の“全て”であるということに尽きるのではないだろうか。
それを時系列で言えば、人は人同士のつながりのなかでこそ生きているということだ。この場合、つながりとは言っても、単純な直流ではなく、複雑な配線を持つ交流なのである。
私はなぜこれを書いたのだろうか? もちろん何かを伝えたかったからである。
では、何を伝えたかったのだろうか? 書いたことの全てであり、書かなかったことの全てである。
書かなかったことが伝わるわけがないと思われるかもしれないが、書いたことだって伝わるかどうか、それは私にさえわからない。
別の言い方をしよう。
何かを書き表すということは、別の何かを書き漏らすということでもある。ただ、書き表そうとすることはその場で意識できているが、書き漏らしたことはその場では意識できていないから書き漏らすことになるのだ(あとからは意識すれば思い出せるが…)。
もしこの文章を読んでくださった方がいるのなら、私が書いたことと同時に、私が意識できずに書き漏らしていることは何かということも、私に代わって想像していただきたい。そして、「こんなことを書き漏らしていませんでしたか?」、「あんなことを書き漏らしていませんでしたか?」と、いつか私に教えてほしい。そこに潜在的な対話の回路が成立したら、面白いではないか。
おそらく私が何かを伝えたいと一番に思っている相手は、次の世代を創っていく人たちである。しかし私は、伝えたい、知ってほしいと思うことを、押しつけるべきではないとも思っている。書かれたことは書かれた瞬間に書き手の元を離れ、読み手のものになるからである。

ただ、私はこの文章を読んでくださった方とは、「友人」になりたいと思っている。なぜなら、この文章を読むという行為を通して私に出会ってくださったからだ。
その意味では、読んでくださった瞬間に、あなたは私の文章の「宛先」となり、潜在的な「友人」の一人になってくださったのだと思う。
その先、私たちが本当の「友人」になれるかどうかはわからないが、そのきっかけがこのインターネットという仕組みのなかで生まれつつあることだけは確かではないだろうか?
「世界の目的は友人を創ることにある」と、一人の年寄りとなった私は、最近、心から思い始めている。そのためにこそ、私はここで「言葉を語る」という場所に行き着いた思いがする。
読んでくださった全ての方に、感謝を申し述べたい。
そして、こう言ってお別れすることにしたい。
「いつか、また、どこかで」
───【完】───